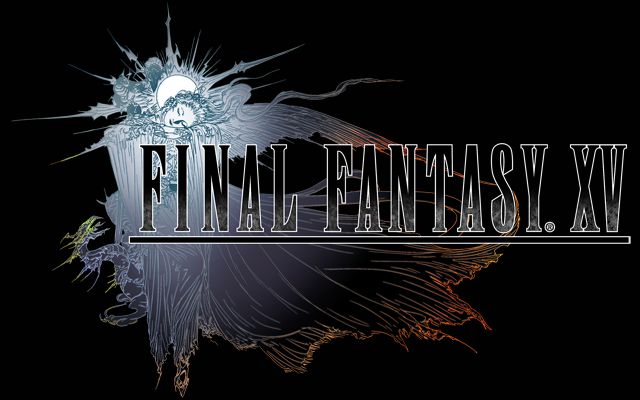高くても面白いとは限らないのがゲームです。
結局は、合うか合わないか
ゲームの価値は人それぞれ
AZです。「三國志13」を購入しプレイしたわけですが、なかなかにアレ過ぎて“何をどう遊べば最高に楽しいのか”だけを模索し続けている状態です。……うん、つまりはそういうことなので、察して下さるとレビューしやすくなる所存です。
さて、2016年1月24日~1月30日までの間に一番閲覧数が多かった記事は、「欧米でコーエープライスが話題になっているようです」でした。なんでしょう、皆様はコーエープライスが好きなのでしょうかね? まぁそんなわけで、価格から見るゲームの価値なるモノを軽く振り返ってみようかと思います。
だからこそ、「自分は」どう思うのかが重要
元々は、海外メディアのKotakuがSteamで発売されたばかりの「三國志13」が89ドルという高額(海外では非常に高い)にも関わらずランキング上位に食い込んだ、というのを紹介したわけですが、コーエーは伝統というべきかわかりませんけど、同社の代表作「三國志」シリーズや「信長の野望」らは高値水準で売るという販売手法を選択しています。まぁ、それに乗るか反るかは人次第で、ぶっちゃけ拡張となる“パワーアップキット”が発売されるのも定番なので、それを待つのが無難な選択だったりもするのですけど。
ゲームの価格というのは、その人が持ち合わせる価値へと変換されます。ある意味、定価で買うというのは早期アクセスのようなモノで、「今」話題のゲームを「すぐさま」やりたいという欲求を満たすモノこそ「定価」と言っても過言ではありません。その時、旬なゲームを遊びたいという欲求は、新しいゲーム大好きな人達なら理解せざるを得ないモノではないでしょうか。
で、定価が高いとなるとそれ相応の内容を求める事になります。要するに、“高いなら高いなりに面白いモノを寄越せ”という要求です。対価を払っている以上は当然のことですが、その基準というのは人それぞれですべてがすべて面白いと判断するのは難しい。だからこそ、ブランドを信じたり、メーカーを信じたり、雑誌や誰かのレビューを信じたりして判断をするのが、現代のゲームに対する情報集めといっても良いでしょう。
ゲームに限った話ではありませんが、高い買い物をする際に慎重に選ぶというのは多くの人がやることであり、それ相応にきちんと調べてから購入を決意するというのがいわゆる「失敗を減らすための買い物」というヤツだったりもします。コーエープライスをどう思うかは人それぞれですが、払うだけの価値があると思える様なクオリティになって欲しいと切に願いたい限りですね。